〔注意〕あなたが経験した工事でないことが判明した場合は失格となります。
| 〔注意〕 | 「経験した土木工事」は,あなたが工事請負者の技術者の場合は,あなたの所属会社が受注した工事内容について記述してください。従って,あなたの所属会社が二次下請業者の場合は,発注者名は一次下請業者名となります。 なお,あなたの所属が発注機関の場合の発注者名は,所属機関名となります。 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 〔設問2〕 | 上記工事の現場状況から特に留意した工程管理に関し,次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。 (1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題 (2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容 (3) 技術的な課題に対して現場で実施した対応処置 |
解答と解説:
なお,選択した問題は,解答用紙の選択欄に印を必ず記入してください。
| 〔設問1〕 | 鋼矢板土留め工による掘削時の留意事項に関する次の文章の |
| (1) | 掘削の進行に伴い,掘削面側と鋼矢板土留め壁背面側の力の不均衡が増大し,掘削底面の |
| (2) | 透水性の大きい砂質土地盤で鋼矢板土留め壁を用いて掘削する場合は,掘削の進行に伴って土留め壁背面側と掘削面側の水位差が徐々に大きくなる。この水位差のため,掘削面側の地盤内に上向きの浸透圧が生じ,この浸透圧が掘削面側の地盤の有効重量を超えるようになると,砂の粒子が湧きたつ状態となり,この状態を |
| (3) | 沖積粘性土地盤のような軟弱地盤の場合には,掘削の進行に伴って鋼矢板土留め壁背面の土の重量などにより,土留め壁背面の土が掘削底面へ回り込んで掘削底面の隆起,土留め壁のはらみ,周辺地盤の沈下が生じる。この状態を |
| (4) | 掘削底面下に粘性土地盤や細粒分の多い細砂層のような難透水層があり,その難透水層の下に水圧の高い透水層が存在する場合は,掘削底面に |
| (5) | これらの掘削底面の破壊現象に対して,掘削底面の隆起状況を その計測管理の主な留意事項として, |
|
解答と解説: |
||
| 〔設問2〕 | 切土法面の施工に関して,施工中において常に崩壊や落石の前兆を見逃さないようにしなければならないが,そのための施工時の法面のチェック項目について2つ解答欄に記述しなさい。 |
解答と解説:
| 〔設問1〕 | コンクリート打継目の施工に関する次の文章のに当てはまる適切な語句を解答欄に記入しなさい。 | |
| (1) | コンクリート打継目には,水平打継目と鉛直打継目がある。 | |
| (2) | 水平打継目の施工にあたっては,十分な強度,耐久性及び水密性を有する打継目を造るために,既に打ち込まれた下層コンクリート上部の 既に打ち込まれた下層コンクリートの打継面の処理方法には,硬化前と硬化後の方法がある。 硬化前の処理方法としては,コンクリートの 硬化後の処理方法による場合,既に打ち込まれた下層コンクリートがあまり硬くなければ,高圧の空気及び水を吹き付けて入念に洗うか,水をかけながら,ワイヤブラシを用いて表面を(ニ)にする必要がある。 |
|
| (3) | 鉛直打継目の施工にあたっては,硬化後の処理方法による場合,既に打ち込まれ硬化したコンクリートの打継面は,ワイヤブラシで表面を削るか,チッピングなどにより |
|
解答と解説:
| 〔設問2〕 | コンクリートに特別の性能を与えるために,打込みを行う前までに必要に応じて加える混和剤(JIS A 6204,JIS A 6205に規定のもの)を2つあげ,その目的を解答欄に記述しなさい。 |
解答と解説:
| 〔設問1〕 |
| (1) | 試験施工は,本施工を行う前に小規模な施工を行って,設計で想定した盛土の要求性能を確保できるかを事前に把握するため,あるいは設計で想定した盛土の要求性能を確保できる 工事期間内において施工の |
|
|
|
| (2) | 標準的な締固め試験施工の実施方法については,工事区間の代表的な材料を使用する。 土の締固め含水比は自然含水比とし,調整が可能であれば突固め試験の 締固め回数については,10 数回程度で締固めが完了するようにする。 |
|
解答と解説: |
|
|
|
|
| 〔設問2〕 | コンクリートに発生した次のひび割れの状況図からひび割れの名称を2つ選び,各々のひび割れの原因と防止対策を記述しなさい。 |
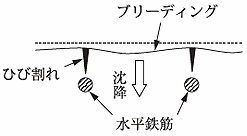 |
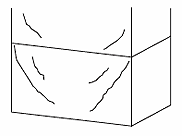 |
||
| (1) | 沈みひび割れ | (2) | 乾燥収縮ひび割れ |
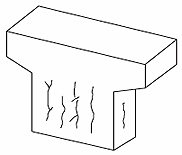 |
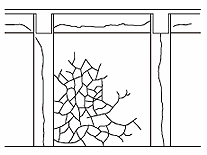 |
||
| (3) | 水和熱によるひび割れ | (4) | アルカリシリカ反応によるひび割れ (膨張ひび割れ) |
解答と解説:
| 〔設問1〕 | 降雨,融雪又は地震に伴う土石流の発生や急激な水位上昇が発生するおそれのある河川において,建設工事の作業を行うとき,土石流や急激な水位上昇などの発生のおそれのあるときに発生を早期に把握する必要がある。 労働者を避難させ安全を確保するために,事業者があらかじめ定めておかなければならない事柄について,労働安全衛生法令及び土木工事安全施工技術指針に基づいて3つ解答欄に記述しなさい。 |
解答と解説:
| 〔設問2〕 | 高所での作業において,墜落や飛来落下の災害を防止する対策を5つ解答欄に記述しなさい。 |
解答と解説:
| 〔設問1〕 | 施工計画の立案に留意する事項についての次の文章の |
| (1) | 施工計画は,施工の安全性を前提として工事の工期,経済性及び |
| (2) | 安全施工の計画には,工事の難易度を評価する項目(工事数量,地形地質,構造規模,適用工法,工期,工程,材料,用地など)を考慮し,工事の安全施工が確保されるように総合的な視点で作成する。 また,設計図書及び 関係機関との協議・調整が必要となる工事では,その協議・調整内容をよく把握し,特に都市内工事にあっては, |
| (3) | 環境保全計画の対象としては,建設工事における |
解答と解説:
| 〔設問2〕 | 施工者が建設廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき,一時的に現場内保管する場合,周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするための具体的事項(措置)を5つ解答欄に記述しなさい。 ただし,特別管理産業廃棄物は対象としない。 |
解答と解説: